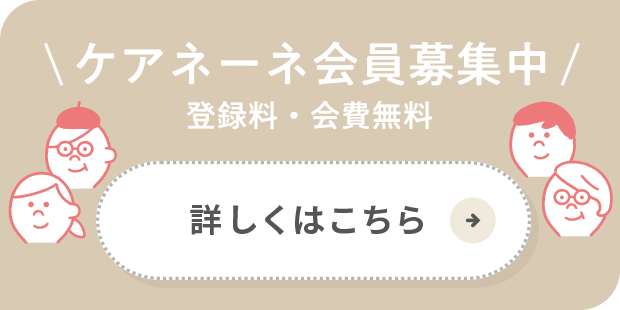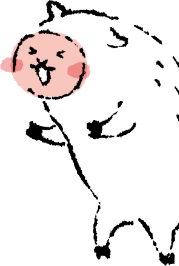昔ながらの原風景が広がる、奥信濃の北志賀高原。 その里山にある「夜間瀬あけび工房」の管理人、松本百合子さん。 自然の中で生き、山とともに暮らす百合子さんとおしゃべりしていると、 いつものように、季節の手しごとがはじまりましたよ。 さあさあ、夜間瀬あけび工房の囲炉裏端へ、みなさんもどうぞ、ごいっしょに。


農家のお嫁さんをねぎらう笹餅づくり。
百合子さんが大切にしている歳時記(季節の行事)のひとつ「野休み」。
夜間瀬あけび工房で、いつもの仲間たちと野休みの笹餅を作ると聞き、さっそくお邪魔しました。小学生からおじいちゃん、おばあちゃんまで集まって、今日の工房はとても賑やかです!


「昔はね、田植えが終わったころ、農家のお嫁さんは“野休み”って休みをもらって、実家に帰ってたんだって。それで、“畑仕事ご苦労様でした”って笹餅をついて、それを持たせて帰らせたんだよ。お嫁さんたちは、近所の田植えまで手伝って、本当に忙しかったからね」。
そもそも、笹餅は北信濃の伝統食なのだそう。百合子さんが近くから採ってきた信濃笹を、1枚1枚キレイに拭いていきます。

この、ちょっと長めの茎に葉っぱが2枚ついているのはどうして?
「2枚の葉っぱでお餅を挟むんだよ」。

なるほど!北信濃に伝わる笹餅は、昔は軒先に吊るして干し、非常食や子どものおやつとしても食べられていたのだとか。笹の葉にはカビの発生を防ぎ、保存性を高めてくれる防腐・殺菌効果があるのですが…。
「今の新建材の家に吊るせばすぐにかびるよ」と百合子さん。やっぱり、昔ながらの山の家には、木の持つ自然の力が生きているんですね。
みんなで作って、みんなで食べる。
貴重な集いの場を、次の世代へ。
今ではあまり見かけなくなった木の臼と杵で、ぺったん、ぺったん、いい音が工房の庭に響きます。
お餅がつきあがったら、熱いうちに丸めて笹の葉に挟んでいきます。ほかにも、きな粉、あんこ、大根おろしで味をつけたお餅は、1枚の笹の葉でくるっと巻いて。炭火の上の根曲がり竹も焼き上がって、おいしそうな地元の山の幸がいっぱい!




百合子さんの、みんなをねぎらう挨拶のあとは食事タイムです。
「これは、長芋にシソと梅の実をあえてあるんだよ」
「おいしいね」
「すごい量のお餅だねぇ」

…ワイワイと大勢でテーブルを囲んで、みんなで作った笹餅を、みんなで食べる。この楽しさ、心がじんわり和んでいく感じ、久しぶりに思い出しました!
一昔前は当たり前だった風景が、ここ山ノ内町でも貴重なものになっています。ゆりこさんが次の世代へつなぎ残していきたいのは、季節を刻む喜びをみんなで分かち合う、心豊かな時間なのかもしれません。
「歳時記は、祈りとねぎらいの行事なんだよ。だから、山の暮らしの楽しみと同時に、厳しい季節を乗り越えられる力をも得られる気がするんだよねぇ」。


祭りも米作りも、後継者不足が問題に。
「野休みもだんだんとなくなってさ。ほら、今はみんな車でいつでも実家に帰れるでしょ。それでも田植えが終わったら、みんなで一休みしましょうって、村対抗でバレーボールや野球大会やってたの。村中で応援に行ってね。それも、コロナでなくなっちゃったけど」


「嫁に来ると、“バレーボールできるか?”って聞かれるのよ。私、背が高かったからさ」と、工房仲間の北澤啓子さん。百合子さんとは、夜間瀬あけび工房ができる前からのお付き合いで、北澤さんもよく工房で陶芸や竹細工を楽しんでいました。百合子さんいわく、「陶芸のセンスがイイ」のだそう。
「復活させようにも、もうみんな体力がないからねぇ。お祭りもやらなくなったしね」。
「お祭りの時は、お宮の前に立派な提灯が連なっていたけど、もう組み方がわからなくなっちゃって、壊れても直せる人がいないもんね。土橋の神楽もやらなくなったし」。北澤さんが住む地域の諏訪神社には古くから伝わる神楽あり、山ノ内町の無形民俗文化財にも指定されています。
「前は秋祭りにお獅子が一軒一軒回って、厄払いしてたんだよ」。
コロナ禍以降、日本各地の多くの祭りが消え、さらに少子高齢化で祭りの継承も難しいといいます。
※お話に出た神楽は2025年秋祭りで復活させようという話も出ているようです。

後継者の問題は米づくりにも。北澤さんが嫁いできた昭和50年代に耕地整理が進み、同時に機械化が一気に進んでいきました。作業が楽になった一方で、徐々に荒れた田畑が増えていったそうです。
「一時は水田もいっぱいあったけど、半分くらいに減っちゃった。あとを継ぐ人がいないからね。急激に車社会になったから、みんな外に仕事を求めに出てしまった。会社勤めして、米は買ってるんだよ」
減反政策の影響もあり、夜間瀬地区では米の代わりにリンゴやブドウ、キノコなどを生産する農家が増えたのだとか。しかし、北澤さんの住む須賀川では果樹を作ることが難しく、離農する人が多かったようです。米不足、米高騰が深刻化している今、農家の後継者不足は他人事ではなくなってきています。
「ほんと、米はどこに行ったんだろうね。果樹は農家さんがネットで直接個人に売ったりしてるじゃん。米がなかなかそうならなかったのは歴史だと思うよ。「供出米」って言葉知ってる?戦争中から戦後も、農家は国に強制的に米を提供しなければいけない制度があったから、個人での販売が遅れたんじゃないかなぁ」。
旅人を惹きつける、
昔ながらの風景とおもてなしの心。
「昔は、雪が降ると仕事にも行けなくて、毎朝遅刻してた。除雪されないから、渋滞がすごかったんだよね」と北澤さん。
スキーブームが訪れた昭和60年代ごろから道路の整備も進み、民宿も増えてきたそうです。近年、白馬村に国内外からの観光客が爆発的に増えたと話題になっていますが、最近では日本の原風景を求めて、山ノ内町を訪れる外国人観光客も多くなってきました。そんな海外からの旅人を日本的なものでおもてなししようと、須賀川そばのそば打ち体験や、民具を展示した資料館もあるそう。野沢温泉にあるスーザンとピーター(ダーニングで紹介した、百合子さんの工房仲間)の宿にも、百合子さんたちが作った、帯をリメイクしたティッシュケースやさるぼぼが飾ってあります。
単なるサービスではない、心のこもったおもてなし。皆さんの、誰かを喜ばせたいという思いが伝わってきました。
百合子さん、また来年の「野休み」を楽しみにしています!集い、つながり、ふるさとをあらためて思う機会をありがとうございました。
笹餅の作り方
1 笹は2枚一組のものを用意する。



2 餅を小判型にして葉っぱの上に置き、もう一枚の葉ではさむ


※砂糖醤油やきな粉など、食べる時にお好みの味をつけます。
※市販の餅でOK。耐熱性の器に餅を並べ、餅がかぶるくらいの水を加えてラップをせず600ワットで1分~1分半ほど硬さを見ながら加熱してください。
お餅3種
1 餅を大きめのピンポン玉くらいに丸める


2 きな粉、あんこ、大根おろしにからめて笹で巻く



●きな粉
きな粉2:砂糖1の割合で混ぜる。塩を少々加える。
●あんこ
材料 小豆200g 砂糖100~200g(好みで加減)
①洗った小豆をたっぷりのお湯でゆでる。
②沸騰したらザルにあげてゆでこぼす。これを2回ほど繰り返してアクを抜く。
③小豆がしっかりかぶるくらいの水を入れ、アクを取りながら弱火でコトコト煮る。
指でつぶしてみて柔らかくなったら、砂糖、塩少々を加えて水分を飛ばしながら煮る。
●大根おろし
大根をすりおろしたらザルにあげて軽く水分を切る。味を見ながら醤油を加える。
百合子さん流☆味の決め手
割合いなんていいかげん!! なめてみて決めればいいんだよ。
あんこの甘さは市販の半分位かな?甘いっていうより、小豆の味がしっかり生きるようにしてるんだよ。
松本 百合子さん
名古屋生まれ。短大卒業後、保育士として名古屋、東京で働く。結婚を機に北志賀高原の夜間瀬へ。二人の娘を育て、現在は夜間瀬あけび工房の管理人として、山で暮らす知恵や伝統を楽しみ、つなぐ場を地域の人とともにつくっている。私はすべてが「なんちゃって」で「いいかげんなんです」が口ぐせ。
百合子さんのブログ
夜間瀬あけび工房
障がいのある人もない人も、若者もお年寄りも、みんなでこれからの楽しさを創造しよう!と、2003年百合子さんを中心に機織りや陶芸を創作している人たちが開設。築100年を超える古民家でさまざまな手仕事が体験できる。工房展やそば打ち講習などのイベントも開催。